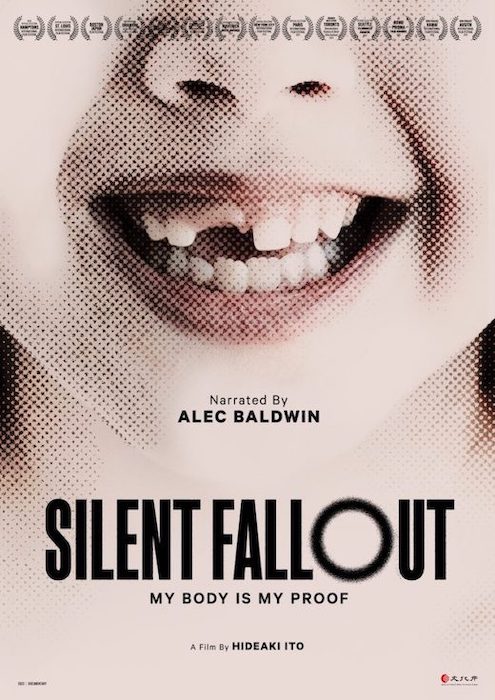「君は、ヒロシマの何も見てはいない」 (Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien)。
「私は見たわ、ヒロシマのすべてを」 (J'ai tout vu. Tout)。
日仏合作映画『ヒロシマ・モナムール』 (Hiroshima, mon amour: 監督 アラン・レネ 1959年) の劇中、繰り返し交わされるこのアンビバレントな台詞は、広島と関わって以来、私の脳裏に常にぶら下がり、三半規管を揺さぶり、手足を突き動かして来ました。
広島と契りを結んで10年余り。広島生まれでも育ちでもない私にとって、その道程は”無知の知”の連続でした。膨大な文献史料を繙き、数多くの当事者から直接体験談を伺う度に、新たな無知がひょっこりと顔を覗かせ、半可通な”知識”は忽ち打ち壊され、さらなる迷宮へと引きずり込まれる。そうした日々の繰り返しであったように思います。「私は、ヒロシマの何も見てはいない」。
その一方で、地元メディアや研究者がこれまで知り得なかった、または見て見ぬフリをして来た歴史的事実を掘り起こし、書籍として初めて記録した自負はあります。「私は見た、ヒロシマの真の姿を」。
広島は、”被爆80年”を迎えました。「80」という数字は、単なる節目、通過点に過ぎません。時計の針は止まることなく、これからも「85」、「90」と年月を刻んで行くことでしょう。ただ、広島では昨秋頃から、日本原水爆被害者団体協議会 (日本被団協) のノーベル平和賞受賞と相俟って、静かなる期待感、一種の高揚感が漂っていたのは事実です。
ところが、”被爆70年”に私が見た光景と「80」とでは、何かが違っていた。広島を取り巻く”空気”は明らかに変貌を遂げていました。マスメディアは、例によって「原爆の日」をほんの半日足らずで”消費”し、取り立てて目新しい切り口を提示することもなく被爆地を後にし、各紙の社説は判で押したかのように定型句の「被爆体験を継承することの大切さ」を説く。論説委員でさえ「戦争」、「被爆」の実相を最早知らない時代。おざなりの言説空間は、その度合いを増しているように感じられました。
“被爆80年”と銘打った催しも全国各地で開かれました。その大半が毎年恒例のルーティンワークで、果たしてこうした型通りの、ある意味、保守的なプレゼンテーションで「戦争」や「原爆」とは無縁の若者たちや外国人の心を動かすことは出来るのだろうか。中には、明確なヴィジョンも正確な知識も、被爆地に寄り添う心根もなく、安易に「80」を掲げ「原爆」を騙ったかのような展示も見受けられました。日本人の意識の劣化は、被爆体験の風化を遙かに凌ぐ勢いで進んでいます。
私にとっての「広島」は、「生」と「死」を考える教室でした。若き日に紛争地や難民キャンプを訪れ、戦時における「死」は少なからず垣間見て来ました。一方、「広島」では、「生」について学びました。原爆によって親兄弟を始め愛する親族や恋人、友人を悉く殺され、自分だけが生き残ってしまったことに対する罪悪感に苛まれながらも原爆症と闘い、さらには壮絶な社会的差別を受けても尚、生き続けるということ。
「生きる」とはどういうことなのか。私は、被爆者との”対話”を通じて、その一端に触れたように思います。「私は、ヒロシマの何も見てはいない」が、「ヒロシマの真実を垣間見た」。
こうした「広島」を取り巻く状況の変化は、被爆地と真摯に向き合っては来なかった大半の”よそ者たち”だけの責任でしょうか。マスメディアの無関心、浅薄を責めれば事足りるのでしょうか。
私は、拙著『平和の栖〜広島から続く道の先に』の中で、広島の戦後は「断絶」と「停滞」の繰り返し、と書きました。常に「利便性」が「歴史性」を凌駕し、両者を融合させ「新規性」を生み出すほどの発想は、ついぞ広島からは創造され得なかった。まるで『ヒロシマ・モナムール』に登場する決して交わることのない会話のように。アイデンティティを喪失した片翼の街の”のっぺらぼう化”は留まるところを知らない。今や、大半の広島市民も「ヒロシマの何も見てはいない」。
被爆80年の夏。広島には”あの朝”と同じように青空が拡がっています。子供たちの無邪気な笑い声が響き渡っています。それでも、「君は、ヒロシマの何も見てはいない」という囁きが私の耳から離れることはありません。それが「広島」を知ってしまった者に科せられた、ある意味、哀しい宿命なのでしょう。